新規交換編の次は電灯管交換編。はーじまーるよー
次は従来の40W蛍光灯型のLEDに交換します。
全部新規ってのが一番いいのはわかってるんだけどあんまり使ってない部屋とかはできるだけお安くってことで器具はそのままで球だけ交換です。
という訳で蛍光灯型のLEDに交換する際の注意点はそのLED蛍光管の給電方法
蛍光灯の口金はG13(2端子以上で端子間が13mm)それが左右にあるので給電方法として片側給電と両側給電の2パターンがあります。
片側給電は接続端子が片側で済むメリットがありますが片側給電にしたユニットに両側給電の蛍光灯型LEDをつけると回路短絡しブレーカーが落ち最悪火災になります。
逆に両側給電は接続改造が両側と面倒ですが間違えて片側給電の蛍光灯型LEDを装着しても事故の起きる可能性は低くなります。(製品によるのでゼロではないよ)
今回は会社管理の会議室ということで”自分以外が交換する可能性がある”ので安全性を考え両側給電のLED蛍光管を採用します。
蛍光灯型LEDはその給電方法さえ間違わなければ後々メーカーが廃盤にしても別メーカーでもほぼ見た目変わらずで使い続けることが出来ます。
今回選んだのは新潟県のリュウドさん。大手メーカーではないものの一応自社企画製品らしいのと本体がガラス製ってことで選びました。
蛍光管本体の材質には
| 材質 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| プラスチック (PE・PET・PS等) | 軽い、安価 | 湾曲する |
| アルミ補強 | 軽く、曲がりにくい | アルミ部分は光が透過しない |
| ガラス | 曲がりにくく、全体が透過する | 割れる |
| 基板むき出し | 遮るものがなく明るい | 光点が強く刺激が強い |
割れるデメリットはありますが元々の蛍光灯もガラス製で割れ物なので問題なし
蛍光灯と重さが違う(重たいから器具に負荷がかかる)とう言う意見も散見しますがそんなに変わりません。
蛍光灯の灯具本体は結局、中身を抜いて再配線して両側給電専用に改造しました。
その辺は電気工事に当たるのでちゃんと工事し免許を持った人がしましょうね!ってことでどう工事するかは割愛。免許持ってる人なら簡単にわかる構造です。
そんな感じで長々と書きましたが無事会議室のLED化工事終了
初期不良もなく、事故もなく、一部には気づいてもらえずでしたがこれで今後の蛍光灯の生産終了にともなう値上げとかのリスクも回避できると思います。
最後に出てきたリスク問題ですが実は数室ある会議室で一部に灯具本体の不具合(昇圧器の故障)があったのですが発覚した当時すでに新品在庫がなく(※商社からは”生産終了”でなく”在庫切れ”とアナウンス)昇圧器のみの交換も検討しましたが純正品はなく灯具本体より高いという始末。
そんなわけで見送っていましたが今回新しく交換できて会議室がちゃんと明るくなりました



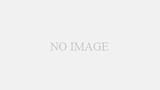

コメント